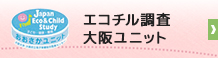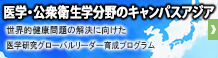大阪大学未来戦略シンポジウム(第五部門【未来共生】)
WHO等の国際機関で働く人材育成の組織化
【趣旨】日本はWHO等の国際機関で働く人材が諸外国に比べて少なく、その理由として、語学力の問題に加えて、雇用制度の相違等が指摘されている。これらの問題を解決するため、欧米における国際機関、国内の行政機関、大学の間での人材の交流がより頻繁に行われている状況を詳細に検討し、国際機関で働く人材を組織的に育成する上での大学の役割と諸機関との連携について議論し、わが国における新しい人材育成の仕組みを探る。
日時: 2013年3月20日
会場: 千里阪急ホテル
- 9:30 - 10:00
- 開会の挨拶
- 10:00 - 10:30
- 講演:WHO等の国際機関で働く人材育成のための大学の役割
- 10:30 - 11:30
- 講演:どのようにして国際保健課題を解決するか?国内保健機関、行政機関、国際機関の役割
- 11:30 - 12:00
- 講演:WHOで働く人材育成のための、厚生労働省の戦略
- 12:00 - 12:30
- 御講演者に対する質疑応答
- 13:40 - 14:00
- 医療保健人材、医療保健サービス拡充、次の2015協議課題を目指して
- 14:00 - 14:20
- WHOと大学から学んだ教訓
- 14:20 - 14:40
- WHOにおける日本人職員の存在感を高めるために
- 14:40 - 15:00
- 国際感染症予防に関する日本人の貢献を高める必要性‐長崎大学における熱帯感染症と新興感染症に対する予防と対策のための国際的リーダ育成への取り組み‐
- 15:00 - 15:30
- 休憩
- 15:30 - 16:30
- ライブビデオ講演:若手医療者が国際保健分野で活躍する際に国際保健の重要性への理解を促す仕組み
- 16:30 - 17:30
- シンポジウム:ディスカッション
- 17:30 - 17:45
- 座長のまとめ
- 18:00 - 20:00
- 意見交換会
9:30 - 10:00 開会の挨拶
- 相本 三郎
- 大阪大学理事・副学長
- 星野 俊也
- 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授
- 松坂 浩史
- 文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室長
10:00 - 10:30 講演:WHO等の国際機関で働く人材育成のための大学の役割
- 磯 博康
- 大阪大学理事・副学長
- 座長:志水 宏吉
- 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授
国際機関で活躍する日本人スタッフを増やしていくため、大学間でのコンソーシアムを形成し、日本の各省庁と連携しながら人材育成を行っていく仕組みについて提起する。
10:30 - 11:30 講演:どのようにして国際保健課題を解決するか?国内保健機関、行政機関、国際機関の役割
- Jousilahti Pekka
- Research Professor of National Institute for Health and Welfare, Finland
- 座長:磯 博康
- 大阪大学医学系研究科公衆衛生学教授
世界における疾患、とくに悲感染性疾患(NCD)についての動向から、国際機関や各国の保健行政機関が協力できることを提案する。
11:30 - 12:00 講演:WHOで働く人材育成のための、厚生労働省の戦略
- 麦谷 眞里
- 厚生労働省国際保健担当審議官
- 座長:祖父江 友孝
- 大阪大学医学系研究科環境医学教授
国際保健分野を扱う組織が多様化していく中で、どのような人材が世界で求められているのか、またそういった人材を育成していくための方策について提案する。
12:00 - 12:30 御講演者に対する質疑応答
聴衆からの『日本人が国際保健分野に関わる時の強みや逆に言語的バリアなどの弱みを克服するためどのようなことをすべきか』について様々なアイデアが呈示された。また、NCD、特に生活習慣病の負担が世界的に大きくなっていく中でそれを予防していくには、文化や社会制度の違う中で国を超えて協力していくためには、どうすべきかといった議論が展開された。
- シンポジウム
- WHOでの経験と人材育成の仕組みに関する提言
- 座長:磯 博康
- 大阪大学医学系研究科公衆衛生学教授
- 新福 尚隆
- 神戸大学名誉教授(医学研究国際交流センター)
13:40 - 14:00 医療保健人材、医療保健サービス拡充、次の2015協議課題を目指して
- 野崎 慎仁郎
- 世界保健医療人材連合 渉外情報官・理事長付 (長崎大学 国際連携研究戦略本部 教授)
世界における医療保健人材の不足にどう立ち向かうべきかをテーマに世界的国際保健医療人財育成の取り組みとその事業検証、そして次なる提案を呈示する。
14:00 - 14:20 WHOと大学から学んだ教訓
- 遠藤 弘良
- 東京女子医科大学国際環境・熱帯医学教授
世界で活躍する若手医療人材の育成には、早期に発展途上国を含む諸外国の健康医療問題へ触れる機会の提供とロールモデルが必要となってくるのではないか、自身の体験を基にした若手へのメッセージを送る。
14:20 - 14:40 WHOにおける日本人職員の存在感を高めるために
- 杉浦 寛奈
- WHO Dept. of Mental Health and Substance Abuse Technical Officer (JPO)
今まさにWHOの精神保健分野で働いている講演者が自身のキャリアパスを振り返り、次なる世代へのエールを送る。
14:40 - 15:00 国際感染症予防に関する日本人の貢献を高める必要性‐長崎大学における熱帯感染症と新興感染症に対する予防と対策のための国際的リーダ育成への取り組み‐
- 森田 公一
- 長崎大学熱帯医学研究所副所長(教授)
世界中を脅かす新興感染症の脅威に立ち向かうため、長崎大学の強みを生かした国際感染症の専門家育成のビジョンを展開する。
15:00 - 15:30 休憩
15:30 - 16:30 ライブビデオ講演:若手医療者が国際保健分野で活躍する際に国際保健の重要性への理解を促す仕組み
- David Heymann
- Professor, London University, School of Hygiene and Tropical Medicine
若手時代にCDCから派遣された自分のミッションを契機に、国際保健分野に関わってきたか、そして、若手医療人材が国際保健に関わっていく機会を広げるための仕組みについて議論する。
16:30 - 17:30 シンポジウム:ディスカッション
- 上記講演者
- [指定発言]松山 章子
- 長崎大学大学院国際保健開発研究科教授
国際保健分野や国際機関で働いていくために、最も大切な資質はなにか。それぞれの御講演者から、様々な意見が寄せられる。自発的に物事を進められること、様々なバックグランドを持つ人々と協力関係を築けること、専門性をもつこと、自分の仕事を心から好きであること、世界の人々と有機的ネットワークを形成すること、使命感をもって仕事に取り組むこと、他者を説得できること、常に学び続ける学習意欲など、講演者のそれぞれの独自の視点が披露される。
17:30 - 17:45 座長のまとめ
<聴講者からの感想> WHO等の国際機関で働くことを目標とする学生にとって、実際に国際機関で勤務経験のある先生方から、雇用されるための具体的な条件や求められる人物像、実際雇用されたものの人によっては環境が合わないこともあるといった現実的な問題等の情報を提供していただく機会を得たことは、非常に有用であった。 感染症や生活習慣病といった幅広いテーマの国際保健分野に関わる道筋について、それぞれの先生の体験をもとにした貴重な話を伺うことができて良かった。また、実際に国際機関等で働かれている先生方から御話を聞くことで、モチベーションを上げることができた。
18:00 - 20:00 意見交換会
意見交換会では、シンポジストの先生方や教員、学生が出席し、活発な議論が行われた。講演会では聞くことが出来なかったお話や、先生方の体験談、国際保健の展望などについて伺うことができ、シンポジウムを締めくくるに相応しい充実した意見交換会となった。