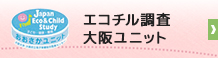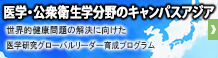沖縄だより
白井こころ

このたび、大阪大学を離れて、沖縄県の琉球大学へ赴任することになりました。大阪 大学では、万博記念公園の緑を眺めながら机に向かっていましたが、琉球大学では亜熱帯のやんばるの森に囲まれ、遠くに海を見ながらお仕事をしています。
沖縄の印象

住み始めたばかりの沖縄の印象は、思っていた以上に独自の文化を堅持していて、琉球王朝時代からの風習や地域行事、食文化などが現在の生活にも、当たりまえに根付いていることに、日々驚かされています。
今もこの原稿を書きながら、校内で沖縄伝統音楽を奏でる三線(サンシン)と太鼓の音がしています。(うーん、毎日旅行気分。)また、ハイビスカスや火炎樹などの熱帯植物が街路樹として街中に茂り、距離的にも台湾やフィリピンなどの東南アジアの国に近く、街中に流れる空気が、時々外国を感じさせます。
那覇からの移動でも、台湾までは飛行機で1時間弱、対して沖縄―大阪間は2時間の距離です。
長寿の島

沖縄は長い間、長寿の島として有名で、現在の高齢者世代は確かにお元気です。平均寿命では長野県が全国1となり、沖縄は女性の平均寿命のみが全国1の状況ですが、県内の100歳以上の長寿者の数では、人口10万人あたり61.03人で36年連続で全国トップです(2008年9月)。
しかしながら、現役世代の健康リスクを考えると、肥満率、喫煙率ともに非常に高く、鉄道網の未整備も一因となり、移動の大半を車に頼る生活です。
これは、運動不足とともに事故死亡率の高さとも関連しています。
また、社会経済的にも、基地問題等もあり、観光以外の地場産業の発達は停滞し、完全失業率は日本1、県民所得は全国最下位です。
こうした状況のなかで、人口の自然増加率は日本1ですが、既に男性の平均寿命はかなり後退し、県全体の平均寿命の低下も予測され、沖縄の長寿県としての性格が変わってくることが危惧されています。
沖縄の金融システム
沖縄らしいといえば、夏に赴任したこともあり、先日旧盆行事に参加しました。3日間の盆期間は、先祖を迎える「ウークイ」の日から始まり、あの世へ送り返す「ウンケー」まで、各家庭での神事とともに、各地の青年会が30人程から成るエイサー隊を作り、先祖の霊を迎え、無事に送るために、踊りと音楽を披露しながら各地域を練り歩きます。
最終日は夜中2時頃まで祭りは続き、子供たちも御爺・御婆と一緒に参加することが珍しくないとか。沖縄には盆暮れ以外にも、地域住民の集まりや、親戚縁者が集まる年中行事が非常に多く、年数回ある先祖供養の機会も多くの人が集まって、賑やかに行われます。亀甲墓と呼ばれる沖縄独自の大きな墓は、墓前に人が集まり、宴会ができるスペースが設けられていることも有名です。

また、沖縄では、摸合(モアイ)と呼ばれる相互扶助の金融システムが今でも盛んです。他地域の「頼母子講」に近く、もともとは、銀行などの公的な金融サービス利用が困難なことから、数人のグループで一律のまとまったお金を出し合い、持ち回りで定例会を開いてきたそうです。
今では、定例飲み会としての機能の方が重要なのかもしれませんが、多様な金融システムが発達した現在も、他にもみられる公的な社会保障サービスを代替する、地域の互助・共助のネットワークとともに、地域の社 会資源の一つとして機能しています。
長寿の理由
沖縄の長寿の理由の一つとして、よく伝統的な食生活が取り上げられていますが、ほかに、地域連帯感や信頼規範の強さ、活発な年中行事の中での高齢者の役割の多さや、地域組織活動の充実など、素直に見れば、個人のネットワークと地域のソーシャル・キャピタルの高さが持つ、健康に関する豊かな社会的汎抵抗性資源が関連しているという仮説もちらりと頭をよぎります。
今後の研究
今まで、ソーシャルサポート等を含めた個人と社会との関係性や、主観的幸福感やSOC、ポジティブ感情等、特に健康や個人のWell-beingに肯定的な影響を持つと考えられる社会心理要因について、興味を持ってきました。沖縄との関連でいえば、沖縄人の楽天的志向や個人レベルでのネットワークの緊密さ、サポートの授受関係にも関連する周囲の人々との信頼感の高さ、また高齢者の社会参加の度合い等は、健康状態にも影響を及ぼすことが長く予想されてきています。また地域レベルの信頼規範など、社会関係資本の豊かさが、健康や寿命に関連することも予測されていますが、その両方をモデル化した疫学的な実証データは限られています。今後、変わりゆくかつての長寿の島で、平均寿命の下降が顕在化するこの時期に、沖縄県の長寿の謎とそれが変化する要因について、社会疫学的な視点を軸に、研究を進めていけたら嬉しいなと思っています。

大阪大学で学ばせて戴いたことを大切に、遅々としたペースではあります が、成果を形にしていかなくてはいけないな・・と思っています。
ゆっくりと時間が流れる沖縄で、最初に覚えた“うちなー口(沖縄方言)”は、「なんくるないさぁ」(何とかなるよ。大ジョブだよ。)でした。
これからどうなることやら、不安に思うことも多いですが、同時に楽しみでもあります。遠い島の教室員ですが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
白井こころ